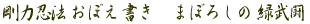
* 僕たちの闘いの章 *
その日、ガイ先生と僕たち〜ネジ・テンテンと僕ロック・リーは、大きな荷物を背負って火の国のとある集落にいたのです。
木の葉の里を出て一週間。里からかなり離れた場所にあるこの町は、シンと静まりかえった所でした。
昼間だというのに、すれちがう人はほとんどいません。
「―あまり、人、住んでなさそうね」
テンテンは道ばたでつんだ一輪の花を僕にさし出しながら、そう言います。
「僕に、くれるんですか?テンテン」
花には興味はありませんが、テンテンの気持ちがうれしくて手をのばします。
「リーにあげるんじゃ、ないの。私の髪にさして」
ああ、そういうことですか。僕は花をうけとって、テンテンの耳の上でまとめた髪の右のおだんごへ、白いその花を両手でそっと飾ってあげました。
「ありがと」
「よく似合ってます、テンテン」
やっぱり女の子ですね。
テンテンはうれしそうに、少しスキップ気味で前を歩いてゆきます。そんな彼女の姿を見ていると、なんだか心がなごみます。
日頃の練習のときに、僕に向ってクナイを鬼のような形相で投げてくる彼女とは、似ても似つかない感じです。
けっこうかわいいです、テンテン。
こうやって、里以外での忍務はツライ事も多いけれど、メンバーの普段とは違う一面をかいま見る事ができるので、なかなか楽しいです。
「――…一羽…二羽……五羽、六羽、七羽」
僕のすぐ前を、何やらぶつぶつひとりごとを言いながら歩いてゆく、ネジ。何かの音におどろいたのか、目の前の空へ鳥が八羽、飛んでいったのが見えました。
「八羽だったか…」
肩を落として、少しさびしそうなネジ。
僕には何のことだかわからないのだけれど、ネジのことだから、独自の修業をやっているんでしょう。そういえば、修業といえば、もうひとり。
僕は立ちどまって、うしろをふり返りました。
あれっ? いない?
さっきまで気配は感じていたのに。
僕は前を歩く二人に声をかけました。
「ちょっと待って。ガイ先生が、いない」
「ウソ!だって、ウサギ飛びでついてきてたじゃない」
テンテンは両手を左右頭の上にかまえ、指先を少しまげてウサギのまねをします。
「そうなんだけど」
目をこらして見てみたけれど、砂ぼこりだらけでガイ先生らしき姿は見えません。ガイ先生は、昨日の修業メニューがこなせていないと言って、目的地までの道中の時間をムダにせず、体力作りをしていたのです。
「ネジ、見てみてよ」
ため息を小さくついて、ネジは目を見開いて白眼の体勢をとりました。みるみるうちに、ネジの目の周りの肌に血管が浮かび上がってきます。
彼のこの能力は、目の前の建物があってもその先のものを見透すことができるのです。
「― くだもの屋の、道を入ったところだ」
僕たちは、今来た道を走って戻ってみました。
食堂・薬局・駄菓子屋・肉屋の隣りにくだものばかりを家の軒下にならべている、店とはいえないような小さな家があります。
盛ったカゴから落ちたのか、道のまん中にリンゴが一コ、足で踏みつぶされたような形で残骸として残っていました。
家の横をのぞいてみようとしたけれど、その奥からは何だかフツウじゃない気配がします。なんだか恐ろしくて誰が一番はじめにその場所を見るのか、お互いにゆずり合うような気持ちになっていました。
僕はテンテンを見、テンテンはネジを見、ネジは僕を見ました。
ネジは無言のまま、あごで気配の方を指します。
゛おまえが、見ろ゛
ネジの目は有無を言わせず、そう言っています。
しかたなく僕は、くだもの屋の角から少しだけ顔を出して道の奥の方をうかがってみました。奥の暗がりには。
体じゅう砂ぼこりで、緑のセットアップスーツが茶色と化して。
おでこと両のほほからは、うっすらと血がにじみ出て。
地面に三角座りをして、両の目から出る涙を、右の手の甲でぬぐっているガイ先生の姿がそこにありました。
ガイ先生のことですから、傷が痛くて泣いているとは、考えにくいのですが。
「先生、泣いてる」
僕は、後ろにいる二人へふり返り、小声で言いました。
ネジが道に落ちていたリンゴの残骸を拾い、僕に見せます。
「コレが落ちていることに気付かずに踏んで体のバランスをくずし、転んだんだろ」
「あ、ウサギ飛び!」
テンテンはひとさしゆびを立ててナルホドというしぐさをし、こっそりとガイ先生の姿を角からのぞきました。
「すごい勢いでぴょんぴょん飛んでたもんね。反復横飛び併用で」
小声でつぶやくのです。
「いつものスピードで地面に顔面からツッ込んだら、さぞかし痛いんじゃない?」
「前ばかり向いてるから、足元がおろそかになる。あの熱心さと速さを追求する姿勢には感心するけどな」
ネジはその方向を見ようともせず、言い捨てます。とはいえ、ネジには最初からガイ先生のその姿は見えていたに違いないのですが。
「悔しくて泣いている姿を俺たちに見られたくないだろう、あの人は」
ネジは横を向き、
「先に行ってる」
と、その場を去ってゆきます。
ああ、そうか。ガイ先生は不注意な自分に悔しくて、涙が出ちゃったんだ。
「ちょ、ちょっと待って。チームは一緒に行動しなくちゃ」
あわてたテンテンは僕の顔を見、少し困った風で、
「リー、あんたが何とかしなさいよ」
「えっ?僕ひとりで?」
「上手くやってよ。ネジと一緒に泊まるところを捜しておくわ」
顔の前で両手を合わせて拝むしぐさをしたテンテンは、僕に全てを押しつけて、ネジのあとを追って行ってしまいました。
どうしようかと考えがまとまらないまま、僕はおそるおそるもう一度、ガイ先生の姿をうかがいました。
先生はひとさしゆびにつばをつけて、ほおの傷を自己流治療中でした。
「あっ、それは不潔です!先生!」
思わず大きな声で言ってしまって自分でおどろき、両手で口をおさえました。でも、遅かった。
「おっ、リー!」
先生は僕の方に顔を向け、舌でなめようとしたその指をバツ悪そうにささっと後ろに隠します。
僕はどうしたらいいかわからず、その場に棒立ちになっていました。
ガイ先生は僕に向って
「キレイ好きな奴に、悪人はいないぞ!」
と訳のわからないセリフを言いました。
そして、半泣きな表情で力なく笑ったのです。口元から白い歯が、ほんの少しだけこぼれて見えました。
ガイ先生は立ちあがると、お尻の砂ぼこりを払いました。僕は走り寄って、先生の体じゅうについている砂をていねいに払ってあげました。
何も言わずに砂ぼこりを払う僕に、ガイ先生は親指を立てたナイスガイなポーズをしてみせてくれました。
少し半泣きで、とても照れくさそうに、です。
僕は今日のガイ先生の三角座りの姿を、いつまでも忘れないでしょう。
でも、僕がいつまでも覚えていようと思ったことは、ガイ先生には内緒です。
タオルをぬらして、先生のほおのすり傷の手当てをしようと、水を捜しに行っていた間に。
自分が踏みつけたリンゴの代金を支払ったガイ先生は、口の上手なおじさんに、リンゴひと山に加えミカンの山盛りも買わされていました。
僕は背負った荷物だけでもけっこう重い上に、両手にリンゴとミカンの袋をぶら下げなくてはいけなくなりました。やじろべえのようなかっこうで、速足のガイ先生のうしろをついて歩いていくのに必死です。
にぎわいの感じられない街の中心地をぬけると、何軒かの旅の宿がならんでいます。こんなといっては何ですが、さびれた所でも旅人をもてなす所があって、僕はホッと胸をなでおろしました。
この街の静けさを見て、てっきり今晩は野宿だろうと思っていたからです。
野宿には慣れていたけれど、やっぱり暖かいフトンで眠れるならその方がいい。ガイ先生も同じように思っていたようで、ミカンを余分に買ったのは、「今晩の夕食だ」と、どう考えても負けおしみのように聞こえる発言です。
「この街は何が名物なんでしょうか、先生」
「ここは観光地ではないからな、リー。それに、遊びに来たわけじゃないんだぞ」
と言うガイ先生の歩みも、野宿しなくてもいいという安堵感で、多少、浮き足立っているように見えます。
とある旅館の軒下につき立っている見覚えのあるクナイ。僕は目ざとくそれを見つけると、
「先生、ネジとテンテンは、ここです」
と、そのクナイをひきぬきました。
「む、そうか。先まわりしていたのだな。感心なやつらだ。ナイスなチームワークだな」
旅館のノレンをくぐって入ってきた僕たちに気付き、帳場から出てきた旅館の主人は、僕たちの姿をチラッと見るなり、
「皆さん、お待ちかねですよ」
にこやかに言います。
部屋へと通されながら、お待ちかねってナンだ?と、つぶやくガイ先生。
「先に来ているネジ達のことじゃないでしょうか」
「おお、そうか」
納得の様子。内心は早くフロに入りたいという感じですね。
僕たちが案内されたのは、三十畳くらいある広間みたいなところです。
「皆さん、すぐ来られます」
主人はそう言い捨てて、大急ぎで行ってしまいました。
僕とガイ先生はそれでも、ネジとテンテンがここへ来るものだと信じて疑わず、荷物を背中から下ろし、そこにあったイスに腰かけて待っていました。
なんだか4人で寝るには充分すぎるくらいの広さだけれど、ここしかあいていなかったのかもしれません。それとも 他のグループとの合部屋でしょうか。しばらくすると 僕たちがいるのとは反対側の扉が開き、ドヤドヤと人がなだれ込むように入ってきました。
ああ、やっぱり合部屋かと思った瞬間、僕は目を疑いました。
人々は、主にお年寄りがほとんどなのですが皆、手に座ブトンを持ち、てんでバラバラに好きなところへと座りはじめたのです。あっという間に広間は多勢の人でうめつくされていました。
しかも、皆、僕というか、正確にはガイ先生と僕を、期待を込めたまなざしで見つめているような気がするのです。
「…な、何でしょう?」
そこへ、主人がスタンドつきマイクを持ってやってきました。
部屋の前方、中央にスタンドをしつらえ、音量を確かめ、テストのような事をしたあとに、
「皆さん、お待たせしました!」
と、正座をしている人たち〜つまり観客に向ってあいさつするのです。
その声に応えるように、
「待ってました!」
とか
「がんばってー!!」
というかけ声と共に、拍手をするお年寄りたち。
僕もつられて拍手をしていると、旅館の主人が僕たち二人の方を向き、こっちへ来いという手まねきをしたのです。
そして、はずんだ声でこう、言ったのです。
「親子マンザイ キュウリーズ のお二人です!」
はっ?
んむっ?
ガイ先生と僕は、自分達の聞き違いではないかと、あたりをキョロキョロ見わたしたけれど、そこにいるのは、ポカンと口をあけた僕たち二人と、拍手をしている旅館の主人。
「あの、僕たちは…」
いつも熱血でものごとを処理してゆくガイ先生も、さすがに困った表情をして途方に暮れています。
主人は、固まって動けないガイ先生と僕を見くらべて、そこでようやく何かヘンだなと気付いたらしく、観客の皆さんに、
「ちょっと失礼」
と言って、僕たちを連れて部屋の外へと出ました。
「マンザイ師じゃなくて、ですね、それに親子でもなくて、いや、親子がイヤっていうわけじゃなくて、コイツは出来のいい自慢の弟子なんですけど、息子というにはちょっと大きすぎないかと。ワタシはこう見えてもですね…」
ツバを飛ばさんばかりの勢いで説明しまくるガイ先生。
その説明を最後まで聞かずに、旅館の主人はのんびりと、
「聞いてた感じとあまりにも違うから、最初見た時、あれっと思ったんだけど。でもおそろいの服装だしねえ。なんたって緑…キュウリーズ…」
おそろいの服装でも、緑の服でも!僕たちマンザイ師じゃありません!
「髪型やらマユゲやら似てるし…でも顔は似てないね、けど、雰囲気似てるし」
親子と言われたガイ先生は、独身貴族を気取っていたのに子持ちに見られ、しかもかなりフケて見えた自分にかなりショックを受けたようです。なんだか雰囲気暗いです。
そんなガイ先生を気にするふうでなく、主人は困ったように、
「せっかく集まってもらったのに…」
主人の話では。
ここの街は老人が多い割に、娯楽があまりないので、マンザイ師やら手品師やらをこの旅館の広間へ呼ぶことが月に一回の恒例行事になっているらしく。
今月の出演者から、ここ2・3日したら着くと連絡があり、そこへ僕たちが現れたので、勘違いをしたということです。
「申し訳ありませんねえ」
頭をかきかき、あやまる主人に、
「誰にでも間違いはあるものです」
と、胸を張って言うガイ先生。
そこへ旅館の従業員らしき人が、駆けこんできました。
「今、連絡が入ったんですが、例のマンザイ親子、ケガして来れないって!」
一瞬、主人の口があんぐりと開いた状態になりました。そしてガイ先生と僕を交互に見ながら、
「困った困った。お年寄りは今日もすごく楽しみにしていたっていうのに。いやね、足の悪い人も体調のすぐれない人も無理してここまで来ていて、今日もダメ。本来のマンザイ親子もダメじゃ、何と説明したらよいのか」
マンザイをしない僕たちが、まるで悪者のようになってしまったようです。なんだかフシギです。
困った困ったと、主人と従業員があまりにもくり返すので、僕も何かお役に立てればなあと思ったのですが、演芸は…。じゃあ、一体何をすれば…。
ガイ先生は無言で何か考えているようですが?
しばらく間があって。
「お役に立ちましょう!」
親指を立てて前へグッとつき出す、ナイスガイなポーズをしたのです。
そして僕の肩をひきよせて、ささやきました。
「いいか、リー。普段おまえがネジとやっている稽古、あれを、やれ」
「ここでですか?」
ネジとの練習は、いつも僕が力およばずとはいえ、結構激しい戦いになるのです。それを室内で、しかも見せものとしてするなんて。
少々ムクれている僕にかまわず、ガイ先生は主人にネジの容貌を伝え、ここへ連れてくるように頼みました。
けれど僕たちは、今日はツイてないようです。
そんな人は、ここへは来ていないというのです。
旅館の前にはテンテンのクナイが目印としてあったというのに。あの二人はどこへ行ってしまったんでしょう。
「どうしましょう、ガイ先生」
オロオロする僕。
ガイ先生は腕組みをして、むむうと考えこんでいたけれど、やがて意を決したように、
「では、リー。俺と勝負だ」
「勝負、ですか?」
「久しぶりにおまえと手合わせをしよう。成長ぶりを見せてくれ」
僕の体術がちかごろ急成長しているとはいっても、ガイ先生と勝負なんてまだ早すぎます。
「よし、俺が負けたら、夕食はヌキだ!」
さっそく自分ルールですか?先生。僕が勝つわけないでしょう。なのにそんな時でも自分ルールを決める、律儀な先生。
僕がおじけづいているにもかかわらず、ガイ先生は助走をつけ、
『木の葉烈風―』
敵もいないのに、しかも一般人のいる室内で、その技は、ガイ先生、あまりにも危険です。
僕はいったい、どうすればいいんでしょう。
Next→ |